最近よく耳にする言葉に「気分が上がる」「気分が下がる」というものがあります。友人との会話やSNSではよく使われていますが、精神科の診療場面ではあまり適切ではないと私は感じています。
「上がる」「下がる」という表現には、どこか自分の外から気分を眺めているような響きがあります。まるで、自分の心をグラフの折れ線のように評価しているかのようです。そのため、本来の「気分」という、身体と心の両方に染み込むような感覚からは少し距離があるように思えます。
実際に診療していると、患者さんが「気分が下がった」と言っても、それがそのまま医学的な「抑うつ気分」を意味することは少なく、むしろ「やる気にならない」「楽しくない」といった自己評価であることが多いのです。
一方で、うつ病の方が自分の気分を語るときには「体が重い」「胸がつかえる」「頭に霧がかかったようだ」といった、身体の感覚に直結する言葉が多く聞かれます。私はこうした表現の方が、気分の本質をよりよく表しているのではないかと思います。
ですから、「気分が上がる・下がる」という言葉は便利ではありますが、心の状態を正確に伝えるには少し不十分かもしれません。むしろ「気分が軽い・重い」という身体感覚に根ざした表現の方が、心の実感に近いのではないでしょうか。
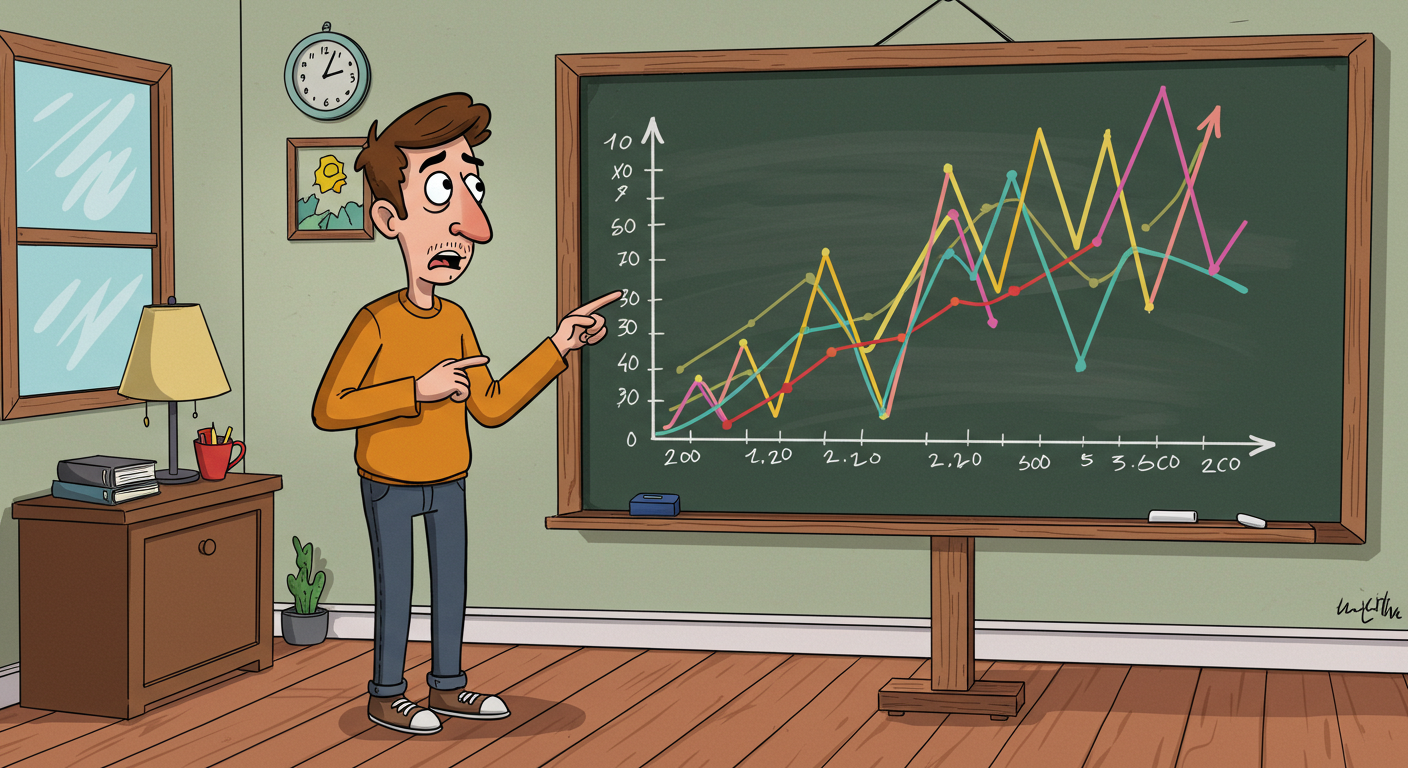

コメント