最近、森田療法学会の中で、外来森田療法をマニュアル化しようという取り組みがあるようです。それ自体が悪いことだとは思いませんが、少しだけ気になることがあります。それは、マニュアルに従うこと自体が目的になってしまい、肝心の森田療法の本質が見えにくくなるのではないか、という懸念です。
以前のブログでも取り上げた「自己一致」という言葉を、ここで改めて思い出していただけたらと思います。心理療法にはさまざまな方法がありますが、基本的な土台には共通する考え方もあるように思います。そのひとつが「自己一致」です。
これは、セラピスト自身が、自分の感情や思いに気づき、それに基づいた言葉や態度でクライアントと向き合う、という姿勢のことを指します。一見するとシンプルに思えるかもしれませんが、この「自分の気持ちに気づく」「それを言動に反映させる」という力は、実は簡単に身につくものではありません。
「誰でもできる」「短時間でできる」精神療法を目指す声もあります。もちろん、そのような取り組みが意味を持つ場面もあるでしょう。ただ、誰もが外科医に向いているわけではないように、精神療法にも「向き・不向き」があると私は思います。薬物療法に強い医師もいれば、精神療法が得意な医師もいる。それぞれが自分に合ったスタイルを選べるのが理想ではないでしょうか。
森田正馬は、「欲望を実現するには、それ相応の苦労が必要だ」と述べています。いまは「誰でも」「すぐに」といった言葉が流行している時代ですが、森田療法のような深い臨床哲学を大切にしたいと考える私としては、「その人の素質に応じて」「時間をかけて」「試行錯誤の末に」体得されていくことも、大切な価値なのではないかと思うのです。

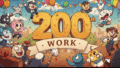
コメント