最近、「睡眠障害は医療機関にかかろう」というキャンペーンを目にする機会が増えました。
確かに、睡眠は心身の健康のバロメーターであり、乱れた睡眠が続けば日中の活動にも支障をきたします。
その意味で、「早めに相談を」というメッセージには一理あります。
けれども、私はこの流れに対して、ひとつの懸念を抱いています。
それは、「眠れないこと=病気」と早急にラベリングし、医療でなんとかしようとすることで、かえって本来の「自然な眠り」の感覚から離れてしまうのではないか、という危惧です。
■ 睡眠は本来、自然に訪れるもの
「どうしても眠らなくては」「思い通りに眠りたい」と強く願うほど、眠れなくなる――
そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
森田療法の視点からすれば、この「眠ろうとする努力」こそが、不眠の根を深める原因となります。
眠りとは、本来、私たちがコントロールするものではありません。
自然な眠気が訪れる条件――太陽のリズム、日中の活動、心身のリラックス――が整えば、自然と眠れるものです。
「あるがままの眠り」を受け入れることが、むしろ回復への第一歩です。
■ 現代社会が妨げる「自然な眠り」
現代の不眠の多くは、「夜も活動を続ける社会」や「乱れた生活習慣」に根ざしています。
人工照明、夜遅くまでのスマホ・PC、昼夜逆転の生活……これらはすべて、生物としての人間のリズムを狂わせる要因です。
つまり、多くの睡眠障害は「医療で治すべき病」ではなく、「自然のリズムから外れた生活の結果」だとも言えます。
であれば、まず見直すべきは、生活そのもの。
朝日を浴び、日中にしっかり身体を動かし、夕方以降は自然に任せて過ごす――
そんな「自然適応的な生活」が、本来の眠る力を呼び戻してくれるのです。
■ 医療化によって深まる「とらわれ」
もちろん、重度の睡眠障害や背景に病気がある場合、医療の介入が必要なこともあります。
しかし、軽度の不眠や一過性の睡眠の乱れまで「病」と捉えてしまうことには、リスクがあります。
「眠れない=いけないこと」という前提が強化されると、眠れないことへの不安が増し、
その不安がまた眠りを妨げる――という悪循環に陥るのです。
これは、まさに神経症的な構造であり、むしろとらわれを深める結果になります。
■ 自然のリズムに身を委ねる――本当の回復へ
私たちの医院では、「自然適応療法」という考え方を大切にしています。
眠りを「操作すべきもの」とせず、自然のリズムに委ねる姿勢を取り戻すこと。
そのために、運動、食事、自然との接点を見直すこと。
それが、心と身体を本来の状態に整える近道だと考えています。
睡眠は、与えられるものではなく「戻ってくるもの」。
「どうしても眠らなきゃ」と焦る心を一度手放してみませんか?


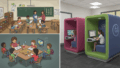
コメント