私が小学生だった頃、昼休みに「掃除の時間」がありました。教室や家庭科室、廊下など、班ごとに持ち場が割り当てられていたのです。
ある日、私の班が担当したのは校庭の掃除でした。同じ班の少年と、ゴミ拾い用のトングを竹刀に見立ててチャンバラを始めてしまい、先生に見つかってしまいました。結果はもちろん「残り掃除」──放課後に追加で掃除をする罰です。
私たちに与えられた課題は、3階の廊下を乾拭きで10往復すること。どうせなら楽しんでやろうと、一緒に残された同級生と「乾拭き競走」を始めました。ところが途中で私は転倒し、脚に擦り傷を負ってしまいます。その時点で残り掃除は中止となり、痛みと共に少し気まずい思い出として心に刻まれました。
そして今朝、なぜかその記憶がふっとよみがえってきたのです。
思い返してみると、あの出来事にはいくつかの意味が隠れているように思います。
- 遊び心と規律のせめぎ合い:人はただ真面目に生きるだけではなく、どこかで遊び心を持ち込みたくなる。
- 罰が楽しみに変わる:課題は苦役でも、工夫次第で「乾拭き競走」という楽しみになる。
- やりすぎ注意:熱中しすぎて転倒し、結局中断。ほどよさを超えると痛い目を見る。
大人になった今も、似たようなことを繰り返している気がします。仕事や生活で課題を与えられるとき、単に「やらされる」のではなく、自分なりの工夫や意味を見いだすことで取り組み方は変わってきます。けれども、ときに張り切りすぎて空回りし、痛い思いをすることもある。
森田療法の観点から言えば、これは「あるがまま」に直面するひとつの縮図です。罰を受けたら受けたまま、課題が出たら出たまま、それをどう扱うかは自分の行動次第。嫌な気分や不満があっても、それを排除しようとするより、工夫して取り組んでみることが大切です。そして失敗して痛みを負ったとしても、それは人生の一部であり、また次の選択へとつながっていく。
子どもの頃の残り掃除の記憶は、そんな「人生の稽古」を小さな形で体験させてくれたのだと、今になって思います。

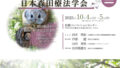
コメント