「そんなに遅くまで寝ていて、遅刻しないの?」
「宿題は終わったの?」
「食べ過ぎじゃない?」
「お酒を飲みすぎじゃない?」
「働きすぎじゃない?」
——こうした声かけを、家族や友人にすることは誰にでもあると思います。大切な人を心配する気持ちから出た言葉でしょう。
しかし、相手自身がすでに「自分の行動に問題がある」とわかっている場合、これらの言葉は逆効果になることがあります。
心配されると「自己調整力」が弱まる
人は、自分の行動が行きすぎていると気づいたとき、どこかで「そろそろやめよう」とブレーキをかける力が働きます。
けれども周囲から「心配の言葉」が繰り返されると、かえって「誰かが見てくれているから大丈夫」という感覚が芽生え、自分でコントロールしようとする力が弱まってしまうのです。その結果、問題の行動がさらに進んでしまうことがあります。
効果的なのは「突き放す」のではなく「委ねる」こと
もし本当に気になるときには、ただ心配を口にするのではなく、少し距離をとった表現が有効です。
「続けていると、体調を崩す人も多いみたいだね」
「そのままだと、後で大変になるかもしれないね」
——このように、あえて“他人事”のニュアンスを残しながら冷静に伝えることで、相手自身が自分の行動を見直す余地が生まれます。
ちょっとしたジョークですが、働きすぎの夫に「働きすぎだから休みなさい」と言うより、
「いっぱい働いて、たくさん遺産を残してね」と伝えた方が、かえって本人が働きすぎに気をつけるかもしれません。
もちろん冗談ですが、それくらい“自分で気づく”きっかけの方が効果的だという例えです。
医師としての経験から
私自身、患者さんの不摂生について「心配してあげる」姿勢は、むしろデメリットの方が多いと感じています。医学的な知識をお伝えした上で、「どう行動するかはあなた次第です」というスタンスを保つことの方が、患者さんが主体的に変わる力を引き出してくれるのです。
大切な人を心配する気持ちは自然なものです。
けれども「心配してあげる」という言葉の裏には、知らず知らずのうちに相手を追い込んでしまう危険があります。
相手の問題を“背負い込む”のではなく、“委ねる”。その関わり方が、相手の変化を支える大切な一歩になるのです。


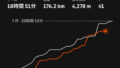
コメント