先日、AHA(アメリカ心臓協会)のBLSプロバイダーコースを受講しました。BLS(Basic Life Support:一次救命処置)は、心肺停止や呼吸停止に対して、胸骨圧迫や人工呼吸、AEDによる除細動を行う緊急対応の基本です。医療者向けの内容ではありますが、本質的には、誰もが行える「命をつなぐ行動」です。
私は精神科医として、これまで入院患者さんの急変時に、胸骨圧迫やバッグマスク換気、AEDによる除細動を何度か経験してきました。しかし、開業してからの8年間は精神科外来を専門にしていたため、救命処置に直面する機会はほとんどありませんでした。
今回、久しぶりにBLSを学び直し、「その場に居合わせた自分が、誰かの命を救えるかもしれない」という現実を、あらためて強く意識するようになりました。
現代では、AEDの使用は一般市民にも推奨され、救命は「医療者にしかできないもの」ではなくなっています。心肺停止からの5分間に何ができるかで、生存率が大きく左右されます。救急車を待っているだけでは間に合わないこともあります。特に、登山中やトレイルレースといった、医療の手が届きにくい場所では、第一発見者の行動がすべてなのです。
屋外で使える資源が限られる状況では、医師も看護師も救命士も、そして市民も、できることにそれほど差はありません。だからこそ、多くの人が「いざというときに、何ができるか」を考え、基本的なスキルを備えておくことが、これからの社会にとって大切だと思います。
精神科医という専門に関わらず、私も一人の人間として、いざ目の前で倒れた人がいたときに、自分にできる最大限の行動を取りたい。そうあらためて思いました。
また最近では、救命に限らず、身の回りのさまざまなトラブルを「専門家に任せる」のが当たり前になっています。家電が壊れれば修理サービス、車が動かなくなればロードサービス、スマートフォンの不具合はサポートセンターへ……もちろんそれ自体は便利で、必要なことです。
けれども、「今この場で、自分にできることはないか」と考える力を、私たちは少しずつ手放してはいないでしょうか。応急処置とは、命をつなぐ技術であると同時に、「自分の力で目の前の問題に立ち向かう」という生き方にもつながっている――私は、そう感じています。

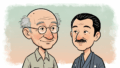
コメント